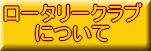2014年06月21日
週報No.48 6月13日分
■会長の時間
井上 勝己会長
司会進行 千葉 康博幹事
歌 唱 君が代、星かげさやかに
髙森 郁子ソングリーダー
来訪者紹介
来賓・卓話者 台北駐福岡経済文化事處
處長(総領事) 戎 義俊氏
渉外課長(副領事)李 蕙 珊氏
熊本火の国R.A.C. 齊藤 友樹会員、春澤 清乃会員
米 山 奨 学 生 葉 (ようりょう)さん
留 学 生 早稲田大学 林 紀 全さん
熊本大学 梁 敏 珣さん
熊本大学 許 意 喬さん
会長の時間 井上 勝己会長
皆様 こんにちは。
今日は大勢のご来訪者を迎えております。私も今日の日をとても、とても楽しみにしておりました。皆さん方とゆっくりこの一時間を過ごしたいと思っております。
それでは、ご来訪者のご紹介をさせていただくわけですが、その前に、一点だけ、本日の例会の主眼を、少しだけお話をさせてください。
本日の例会は、国際奉仕委員会の日ということで企画をさせていただいております。まずもって、このことを皆様方にお伝えいたします。
それでは、ご来訪者のご紹介を致します。
本日の卓話者でございます、台北駐福岡經濟文化事處の総領事・戎義俊(えびすよしとし)様でございます。
このたびは大変ご多用の中を、熊本クラブの卓話を、快くお引き受けを頂きまして、誠にありがとうございます。
当クラブを代表致しまして、心からの感謝を申し上げます。
本日のお話し、大変楽しみにしております。日頃の思いを、どうぞ、熊本クラブの若い方々に、特に今日は、ローターアクトの若い方々にご来訪いただいております。どうぞしっかりとそのお心を、お伝えいただければ、とても有り難く存じます。
よろしくお願い致します。
また、戎総領事は福岡城西ロータリークラブの名誉会員でもございます。当クラブでは県外からご来訪いただいたロータリアンの皆様に対しては、記念品として熊本の伝統工芸品の一つであります「出世コマ」を贈呈する慣例となっています。熊本クラブへのご来訪の記念として、お受け取りいただければと存じます。後ほどお渡しさせていただきます。
続きまして、本日、遠いところを 戎様にご同行をいただいております、
同 渉外課長 李蕙珊塔様でございます。
また、台湾からの留学生で、台湾在日福岡留学生会2014年度会長をなさっており、 現在、早稲田大学大学院に在学の 林紀全さん、でございます。今日は戎総領事と一緒に、福岡から公用車で来ていただいております。ありがとうございます。
次に、熊本大学に、ご在学の 梁敏珣さん
同じく熊本大学に、ご在学の 許意喬さん
でございます。先日4月に開催されました「日台の交流の夕べ」でご一緒させていただいております。今日は、本当にありがとうございます。ゆっくりしていってください。
後ほど留学生を代表して、早稲田大学に在学 林紀全さん、には一言ご挨拶をお願いしたいと思います。
続いて、熊本県 環境生活部 県民生活局 くらしの安全推進課 青少年班 参事 田上清之様でございます。
田上様はグローバルジュニアドリーム事業の担当をされておられ、本年8月に小中高生25名を同行し、台湾に行かれる予定になっています。今日は是非、戎総領事のお話をききたいということで、ご来訪いただいております。
後ほど、グローバルジュニアドリーム事業のご紹介を含めてご挨拶をお願いしたいと思います。
続きまして、米山奨学生 葉(よう りょう)さん でございます。先週に引き続き、ご来訪をいただき、誠にありがとうございます。
最後になりましたが、熊本火の国ローターアクトクラブから2名の方にお出で頂いております。ご紹介します。斎藤友樹様、でございます。春澤清乃様、です。
お二人をはじめ熊本火の国ローターアクトクラブの皆様には、当クラブのことでいつも大変お世話になっています。ありがとうございます。
皆様方のご来訪を心から歓迎申し上げます。
皆様、どうぞ、ごゆっくりとお過ごしいただければと存じます。
本日のご来訪者は以上でございます。
会長の時間でございますが、冒頭に申しあげました通り、本日の例会は、国際奉仕の日ということで、本日の会長挨拶は、ご来訪者のご紹介に代えさせて頂き、国際奉仕委員会の副島委員長に、この後をバトンタッチしたいと思います。
ありがとうございました。
認証品贈呈 井上 勝己会長
国際ロータリーより新会員を推薦により與縄義昭会員へ認証品と贈呈

米山奨学金支給(6月分) 井上 勝己会長
米山奨学生挨拶 葉 さん
新入会員紹介
(推薦者 小堀 富夫会員)

氏 名 原田 耕一
生 年 昭和41年
勤務先 三井住友信託銀行㈱
役職名 熊本支店兼熊本中央支店支店長
趣 味 旅行、ゴルフ
入会2ヶ月以内会員紹介 千葉 康博幹事
岡 成也(熊本YMCA)
■出席委員会
出席報告
■委員会報告
雑誌委員会 丸山 明委員
ロータリーの友 6月号紹介
■トピックス
「国際奉仕委員会の日」
副島 隆国際奉仕委員長
今日は国際奉仕委員会の日ということで、ご挨拶をいたします。
現在、熊本県は、皆様ご存知の通り、いろいろな分野での台湾と熊本との交流を積極的に進めておられます。
特に教育の分野で言えば、熊本ロータリークラブそして熊本南ロータリークラブ、肥後大津ロータリークラブも同行し協力をさせていただきました、3年前の大津高校の台湾修学旅行をきっかけとして、本年は県内高校で、修学旅行先を台湾にしようという大きな流れが出て来ています。
大津高校は3年連続で台湾を修学旅行先として、素晴らしい教育成果を上げておられます。生徒たちも大きな夢と希望を持って帰ってきているようでございます。昨年の同校の修学旅行には、今日取材に来ていただいていますTKUの報道部の方々も同行取材をなさっていらっしゃいます。
当クラブでは3年前の門垣年度に新世代奉仕委員会が、「日台の高校生間の交流・学校間の交流について何かできるもの・あるいは具体的なお手伝いがあれば、これを検討すること」を事業目的に掲げ、当時の大津高校校長白濱先生に卓話者としてご来訪いただき、「物見遊山ではない、真の国際交流に繋げる修学旅行先は台湾が最適である」旨のお話をしていただきました。当クラブの皆様からも高い評価をいただき、具体的な協力・応援の一環として、この時の新世代奉仕委員会の委員長であった井上会長が、先ほどの3ロータリークラブの方々と共に、大津高校の修学旅行に同行されました。
本日はこのような経緯の中、3年度に亘る継続事業の一つとして、国際奉仕のための例会日とさせていただきました。官民が一体となって、将来を担う若い世代の人たちに、様々なことを伝えていこうとする事業に、少しでもお役に立てるならば、これこそロータリーの趣旨・精神にかなうものと言えると思います。本日は、そのような視点で、関係者の皆様のお話を、どうぞ、ごゆっくりお聞きいただければと思います。
最後になりますが、今までのお話の中でもお分かりかと存じますが、本日は、TKUそして、先週卓話をいただきました産経新聞社の方にも取材に来ていただいています。県の事業と台湾の戎総領事をはじめ台湾の官の立場にいらっしゃる方々との連携の様子、その連携の中に熊本ロータリークラブが協力していく姿を、少しでも報道という形で多くの方々に知っていただくことは、本当にありがたいことだと思います。
どうか最後までご清聴のほどよろしくお願い致します。
台湾からの留学生代表挨拶 林 紀 全さん

「グローバルジュニアドリーム事業について」
熊本県くらしの安全推進課青少年班 原田 清之氏

■スマイルボックス
中川 成洋副委員長
井上 勝己、千葉 康博、中島 敬高各会員 本日は、台北駐福岡経済文化弁事所より戎 義俊様ご一行に、卓話のためにご来訪いただいております。感謝のスマイルとともに、お話を楽しみにしております。また、留学生の皆様や熊本火の国R.A.クラブの皆様もようこそおいでくださいました。ゆっくりと楽しまれて下さい。
小野 友道会員 本日、アーンズクラブの皆様が熊本保健科学大学を職場訪問して下さいました。光栄です!!
上田 祐規会員 ①ロータリーから妻の誕生日に可憐なお花を戴き有難うございました。今年、傘寿を迎えた妻のプレゼントはロータリーのお花で代理としました。元気で年をとっていることに感謝しています。②九電の渡邊支店長さんの御栄転をお喜び申し上げます。少し淋しいですが、これからの御活躍をお祈り申し上げます。
小堀 富夫会員 原田耕一さんの入会を歓迎スマイルをいたします。原田さんはロータリーははじめてだそうなので、よろしくお願いをいたします。
目黒 純一会員 ①原田耕一さん、入会おめでとうございます。ゆっくりとしたロータリーライフをお楽しみ下さい。②本日13日(金)と20日(金)の2回欠席します。今日(13日)は韓国・テジョン市のテジョン大学で落成式典に出席してます。20日(金)は、服部胃腸科で定期検診を受けます。4日間入院です。
前原 健男会員 原田さんの入会を心より歓迎いたします。ロータリーライフを楽しみながら熊本のよい所存分にご堪能下さいませ。
原田 耕一会員 本日より、歴史と伝統ある「熊本ロータリークラブ」に入会させていただくことになりました、三井住友信託銀行の原田耕一と申します。初めてのロータリークラブへの入会となります。一生懸命に活動して参りたいと思いますので、皆様にはご指導の程よろしくお願い致します。
中川 成洋会員 本日、弊社の転勤発表がありました。私は引き続き熊本でお世話になります。引き続き熊本で働けること、転勤していく仲間への感謝の気持ちを込めてスマイル致します。
渡邊 義朗会員 九州電力の渡邊です。私、このたびの異動で福岡に転勤となりました。熊本ロータリー在籍は、2年間と短い期間でしたが、皆さまとお知り合いになれて本当に楽しく、充実した熊本生活を送ることができました。厚くお礼申し上げます。また、クラブ会報の委員の方々には、この1年間大変お世話になりました。お陰様で、つつがなく毎週週報の発行ができました。ご協力大変ありがとうございました。最後に、今後の熊本ロータリークラブのますますのご発展と皆様のご健勝を祈念し、心からの感謝の気持ちをこめてスマイルします。「大変ありがとうございました。」
■本日の卓話
卓話者紹介 木下 修例会プログラム委員長
氏 名 戎義俊様
生 年 1953年
学 歴 1972年-1976年 台湾私立輔仁大学日本語科卒業
1983年-1985年 私立慶応義塾大学研究生修士課程1年在籍
2013年3月31日から 台北駐福岡経済文化辨事處處長〈総領事〉
「台湾の『日本精神』から見た日台関係」
台北駐福岡経済文化事處處長(総領事)
戎 義俊氏

台湾人の「日本精神」に関して
一、日本と台湾の結びつき
半世紀にわたった台湾の日本統治時代。「蓬莱(ほうらい)の島」、そして「美麗島(びれいとう)」と呼ばれた台湾で日本人と台湾人がともに過ごした日々の歴史遺産は今も人々に親しまれ、台湾に息づいています。
日本と台湾、その結び付きが大変強いことは言うまでもありません。日本から台湾へ向かう渡航者は年間140万人を超え、台湾から日本を訪れる渡航者は2013年度の実績で230万を数えます。台湾の人口が2,300万人余りである事を考えれば、その数の多さが分かるでしょう。往来の多さだけでなく、心と心の結び付きが強いともよく言われます。東日本大震災の時に巨額の義援金が台湾から送られたことや、インターネットを通じての被災地応援のメッセージなど、日台の結び付きは想像を超えるものがあると言っていいと思います。
二、「日本精神」は台湾では固有名詞として定着している
最近、台湾で『KANO』という映画が大ヒットしています。KANOこと嘉農は正式名称を嘉義農林学校といい、1931年、台湾代表として甲子園に初出場、準優勝を果たした野球部のことです。映画は史実を基につくられており、日本人、本島人(台湾人)、そして原住民からなるチームを一つにまとめ上げ、当初は弱小だったチームを生まれ変わらせた指導者・近藤兵太郎監督の立派な人物像が描かれています。近藤監督役を演じているのは、日本の俳優・永瀬正敏さんです。
『KANO』を通して、日本の教育は素晴らしかったという事が分かりました。「日本の植民地時代を美化しすぎている」という批判もありましたが、台湾が中国に呑み込まれようとしている現在、台湾人が顧みるべきは、この映画で描かれているような「日本精神」であります。この「日本精神」に触れる事を通して、台湾人は中華思想の呪","じゅ">縛","ばく">から改めて脱し、「公」と「私」を区別する武士道的な倫理に基づいた民主社会を確立しなければなりません。「台湾人も日本人もこの映画を見るべきだ」と思い、私からおすすめさせていただきます。
「日本精神」とは台湾人が好んで用いる言葉で「勇気」「誠実」「勤勉」「奉公」「自己犠牲」「責任感」「遵法」「清潔」といった精神をさす言葉です。日本統治時代に台湾人が学び、ある意味台湾で純粋培養された精神として、台湾人が自らの誇りとしたものであります。「日本精神」すなわち大和魂は「拚命(ビヤミア)」「全力を尽くして事に当たる」「命を懸けて行動する」ことの象徴です。「拚」は台湾語で「全力を尽くす」の意味で、「打拚」というと「倦(う)まずたゆまず頑張る」すなわち「勤勉」に通じる言葉であります。
日本の近代教育を受けた台湾人が戦後、目にしたものは中国文化ですが、この時、台湾人は「日本精神」の優位性を見出(みいだ)したのです。そして自ら選んで「大和魂」で精神武装し、内外の厳しい環境を生きようとしているのです。彼らの「大和魂」はひとつの生活の知恵であり、台湾人の魂として生き続ける新たな精神文化なのであります。教育によって台湾に浸透した「日本精神」があったからこそ、台湾は中国文化に呑み込まれず、戦後の近代社会を確立できたと考えられます。私の母は、昔の日本人の先生は、この日本精神で接してくれたと言いました。だから私たちも多少なりともその日本精神というものに染まっているのです。
三、「日本精神」を体現した人物
台湾の農業改革で大きな貢献をした水利技術者の八田与一のことを台湾で知らない人はいません。八田先生は干ばつが頻発していた台湾南部の嘉南平野を徹底的に調査し、灌漑設備が不足していることを指摘して、当時としては世界最大規模である「烏山頭ダム」の建設事業を指揮しました。その後、フィリピンでの灌漑調査のために乗った船が米潜水艦に撃沈されて八田先生は亡くなりましたが、遺骨は台湾に戻り、烏山頭ダムのほとりに眠っています。ダムのほとりの八田先生の銅像とお墓は今では国が整備した公園となって、国民から親しまれています。
日本は1895年4月に台湾総督府を開庁し、そのわずか3ヶ月後の7月に、「教育こそ最優先すべきである」として台北郊外の芝山巖というところに最初の国語学校(日本語学校)「芝山巖学堂」を開校しました。現在では芝山巖は台湾教育発祥の地とされ、「六氏先生」の慰霊碑が建立されています。「六氏先生」というのは、匪族に襲われて殺された6人の日本人教師のことです。危ないことが分かりながらも決して逃げる事のなかった教師たちの責任感と勇気は、教育者としての模範と受け止められ、多くの人から敬(うやま)われました。戦前の日本人は勇気と責任感を持ち、「六氏先生」はその象徴的存在でありました。この「勇気と責任感」こそ、日本人が台湾で尊敬された最大の理由であると私は思っています。「日本精神」というものを究極にするのならば「勇気と責任感」に集約されるのではないかと常々思うのです。教育に命をかけた「六氏先生」の話は台湾ではよく知られ、慰霊碑には今も献花が絶えません。
「八田与一先生」「六氏先生」、他にも台湾のために自らを犠牲にした方々が大勢おられます。彼らに共通するのは「日本精神」を体現した人物であるということです。
これから、日本にも台湾にも、この「日本精神」が脈々と継承され、そしてお互いにますます輝いてもらいたいと祈願します。
四、昔の日本人は素晴らしかった
(一)研究熱心
日本人がすごいところは、何かを研究する時にとことんやることです。何かを真似する時には、日本人はそれを自分のものにして、更に改良を加えてまた別のものを作ってしまいます。しかし、台湾人は見た目だけしか真似できません。外観だけ真似をして、あとは出来るだけ手抜きをするのです。日本人は違います。これはいいと思ったら、グループで一生懸命研究して、その原理を求めて、自分でまたそれに基づいて研究を進めて、更に別のものを作るのです。そこのところが私は立派だと思います。
それから、日本人はお金と時間をかけてでも新しいものにチャレンジします。そして、もう一つ私が立派だと思うことは、日本人はチャレンジしたものを公にして皆で研究します。昔の日本人は、緊急時には皆で力を合わせて、一つのものを四つに分けて、みんなで頂いたものです。自分だけがいっぱい得られればよい、自分だけが大きくなりたい、餓死したくない、という人は少なかったのです。台湾人も苦労してでも、一口のものを半口に減らしてでも人にあげます。
(二)けじめを重んじる
それから、日本人は「けじめ」を重んじます。「はい」といった事は最後まで全うします。日本人は、必ず約束を守ります。そういうふうに私たちは日本人を見てきたのです。
(三)素朴な宗教心がある
昔の日本人が素晴らしかったのは、前の代の教え方が良かったからではないかと思います。つまり、当時の日本人にも更に昔の日本人にも、いわゆる儒教の精神が生きていました。特定の宗教というより、生かされていることをお天道(てんとう)様に感謝し、お天道様に恥じないように生きようという素朴な宗教心があったからこそ、昔の日本人は素晴らしかったのだと思います。
五、今日における日本の若者の問題点
(一)今の日本の問題点は、平和すぎて将来に対する夢がないことなど色々ありますが、一番の問題点は、日本人には、生かされていることに感謝するという素朴な宗教心がないことではないでしょうか。だから自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのかが分からないのではないでしょうか。
(二)今の日本の青年は裕福すぎて考えが甘くなっているのではないかと思います。今の日本の若者は感謝を知りません。喜びを知りません。今、自分がこんなに幸せな国家に住んでいるのにそれを当たり前と思ってしまい、幸せを幸せと思えないのです。正にこれこそが不幸なことではないでしょうか。単一国家でやってきた日本人に生まれたことを、日本の方々は心から感謝しなければならないと思います。この世界には、国を二つにされた経験を持つ国家というものがほとんどですけれど、日本だけが二つにされていないのです。戦国時代といった内乱はありましたが、外国から二つにされた経験はないのです。例えば、中国は八つに分かれていました。ドイツは東西、朝鮮は南北、ベトナムも南北です。私たち台湾人にいたっては、一時国籍のない人間という立場に立たされていたのです。ですから、皆さんは日本人であることに感謝し日本という国を大切にして欲しいと心から願います。
六、台湾と日本、二つとも立派になってほしい
いつも日本の地図を見ていてつくづく思うことがあります。自然の神様は国の形でその国の生き方を教えているのではないかと。ある時にふと地図を逆","さか">さにして見ると、日本が龍に見える、そして台湾はまるで龍を踊らせている火の玉のようだと思いました。この時、この日本という龍について行けば東洋は立派になるんだなと思いました。台湾と日本は同じ火山脈(かざんみゃく)でつながれていて、切っても切れない強い強いつながりがあるのです。
日本がしっかりしなければ、東洋には平和は来ないと私はずっと信じています。日本の経済がよくならないと、世界の少なくともこの東洋の経済は良くなりません。日本という国が強く立派になったら、台湾も立派になります。日本の経済が立ったら台湾の経済も良くなります。そして台湾が良くなったら日本も更に伸びます。
日本と台湾、二つとも立派になって欲しい―これが私の心からの願いです。日本の皆さんが本当に自信を取り戻して、日本のために努力をして欲しいと思います。もちろん台湾も努力を続け、お天道様から見られても恥ずかしくないように立派な国を作っていきたいと思っています。日本と台湾、これからもお互いに切磋琢磨してまいりましょう。
台湾の近代化のインフラ整備のため
犠牲になった日本人たち
~前書き~
今から100年少し前、日本統治時代と呼ばれる1895年からの50年間、かなりの日本人がフォルモサ・麗しき島と呼ばれていた台湾に渡りました。
1898年、第4代総督児玉源太郎の民政長官として赴任した後藤新平が台湾で行った近代化政策は、「生物学の原則に従う」ものでした。元来医者であった後藤は、新領土の社会を一つの生命体として捉え、生き生きとした生命力を引き出す進め方を選択しました。台湾の社会風俗などの調査を行い、その結果をもとに政策を立案していきました。
その具体策として後藤は、台湾の人々の暮らしを豊かにする産業を興すと同時に、港湾、鉄道、道路、上下水道など基本的なインフラの整備に総力を結集しました。そのために内地から各分野で最も優れた人材が呼ばれました。
(「台湾の礎を築いた日本人たち・緒方英樹 著」より抜粋)
これから申し上げる6名の日本人は、自らの命を台湾のインフラ整備のために捧げ、犠牲となられた方々です。ここで簡略に6人の物語を紹介します。
まず始めに「八田与一」技師です。1886年に石川県金沢市で生まれた土木技術者で、1910年、24歳で台湾に渡りました。34歳から10年の歳月をかけて台湾南部の烏山頭に当時東洋一といわれた烏山頭ダムを作り、15万ヘクタールの嘉南平原に灌漑用の水路を張りめぐらせ、不毛の地と呼ばれていた平原を台湾最大の穀倉地帯にかえました。その灌漑用水路の長さは16,000㎞(地球半周分の長さ)に及び、日常的な生活用水にも困り苦しんでいた60万人を超える農民の生活を助けました。ダム完成の一年後には、作業着姿の八田与一の銅像が人々によってダムを見下ろす丘の上に設置され、その功績と精神は後世に伝えられています。
八田は、その後も台湾各地で産業開発に参画していましたが、1942年、南方開発派遣要員として船でフィリピンに向かう途中、アメリカ海軍潜水艦に撃沈され56歳で亡くなり、遺骨は台湾に戻りました。その3年後、終戦をむかえた年の1945年9月1日、32年間八田と暮らした烏山頭で妻の外代喜(とよき)夫人は夫の後を追うように烏山頭ダムの放水口に身を投げました。享年45歳でした。八田の銅像の後方には夫妻の墓碑が建てられ、ダム湖のほとりで烏山頭ダムを見守っています。八田の命日の毎年5月8日には地元の人によって慰霊祭が催され、近年建設された八田記念公園には、外代喜(とよき)夫人の銅像も設置されました。その除幕式には八田技師の長男の嫁にあたる女性が一族を代表して出席されるなど、交流は脈々と受け継がれています。
2人目に「末永仁(すえながめぐむ)」技師です。1886年に福岡県の旧筑紫郡で生まれました。1910年、23歳で台湾に渡り、台中の試験農場で「台湾蓬莱米」の開発改良に心血を注ぎ、自己を顧みず台湾のために尽くされました。1937年からはボルネオ島のサラワク王国に招かれ稲作指導を行っていましたが、指導に邁進するあまり滞在中に結核を患い、1939年台湾に戻りました。その後、台湾での作業中に実験田","でん">で倒れ療養を続けましたが、同じ年の1939年12月に53歳でこの世を去りました。
台湾の風土に適した台湾蓬莱米を開発し台湾の農業を大きく変えた末永技師は「台湾蓬莱米の母」といわれ、台中農事試験場内には、胸像が建てられています。また、出身地である福岡県の農業試験場農業資料館と、大分県の大分県立三重総合高等学校にも胸像が設置されています。
3人目は「飯田豊二」技師です。1873年に静岡県で生まれました。1911年38歳の時、台湾南部の高雄と屏東の境を流れる高屏渓にかける下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋を設計し架設工事に携わりました。工事中に何度も見舞われた豪雨や増水の対処や、寝食を忘れるほど仕事に没頭し続けた結果、下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋の完成を目前に過労による病(マラリア)に倒れてしまい1913年の6月に、鉄橋の完成を見ることなく40歳で亡くなりました。彼の功績を讃えて建てられた飯田技師の記念碑は、今でも下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋を見守り続けています。
4人目は「進藤熊之助」技師です。1874年に茨城県で生まれました。1899年、25歳で台湾に渡り、大変困難を極めた阿里山森林鉄道の測量と建設に携わり情熱を傾けました。その優秀な仕事ぶりが認められ、阿里山作業所の技手(ぎて)から技師に昇格するも、1914年2月に、鉄道修復工事中に材木運搬車が脱線して重傷を負ってしまい、数日後に息を引き取りました。40歳でした。彼は、優れた技術を持つだけでなく誠実で勤勉な技術者であり、私利私情を捨てた働きは多くの人の心を打ち、その功績を讃えるために350人の有志によって寄付金が集められ、嘉義公園内に記念碑が建てられました。
5人目は、「松木幹一郎(まつきかんいちろう)」です。1872年、愛媛県で生まれました。後藤新平の信頼が篤く、1929年57歳で台湾電力の社長に就任し、中断していた日月潭の水力発電事業を再開させ、精力的に水力発電工事に携わりました。自ら歩き回って実地調査を行い、ついに1934年、当時アジア最大の発電量となる水力発電所を完成させました。日月潭第一発電所と第二発電所の完成のため尽力し、1939年、67歳の時に、脳溢血で急逝しました。過労といわれています。一年後の1940年には、その功績を讃えて日月潭に銅像が建てられました(戦時の金属供出により銅像は失われ、現在の胸像は新しいもの)。
後に日月潭第一発電所は大観水力発電所と改名され、その発電量は現在でも台湾の水力発電全体の半分以上を占め、この発電所がなければ今の台湾はないと語り継がれており、「台湾電力の父」といわれています。
6人目は「明石元二郎(あかしもとじろう)」です。1864年、福岡県で生まれました。1918年に第7代台湾総督となり、亡くなるまでの1年4ヶ月の在任中に台湾電力株式会社を設立し、水力発電所の計画を立案、調査に着手しました。また、日本人と台湾人の共学制を採用するなどの教育改革や南北縦貫道路や鉄道の充実など後の台湾の発展に欠かせない大きな業績を残しました。しかし1919年7月、公務で日本に渡る洋上で病に倒れ、郷里の福岡で55歳で亡くなりました。明石の遺骸は「もし自分の身に万一のことがあったら、必ず台湾に葬るように」との遺言通り、福岡から台湾にわざわざ移され、現在も台湾に眠っています。
明石が短期間の在任中に着手した日月潭水力発電事業は、第一次世界大戦による経済不況や関東大震災による影響で10年間中断されていましたが、先に述べました松木幹一郎によって再興され16年がかりで達成され、台湾の工業化を促しました。日月潭水力発電は、1898年から1906年までの8年8ヶ月間、民政長官として台湾の土台を築いてきた後藤新平が描く台湾インフラ整備のクライマックスともいえる大事業でありました。
これまで台湾の近代化のインフラ整備のため自己を顧みず犠牲になった6名の日本の方々の物語について紹介しましたが、備考としてインフラ整備のためでなく台湾の教育のために犠牲になった6名の教師を紹介します。「六氏先生」というのは、日本統治が始まってすぐの1895年7月、「教育こそ最優先すべき」と台湾に設立された小学校「芝山巖学堂(しざんがんがくどう)」で、抗日事件により殺害された6人の日本人教師、楫取(かとり)道明(山口県出身38歳)・関口長太郎(愛知県出身37歳)・中島長吉(群馬県出身25歳)・桂金太郎(東京都出身27歳)・井原順之助(山口県出身23歳)・平井数馬(熊本県出身17歳)のことです。
当時の台湾では日本統治に反対する勢力が激しい抵抗を続けていました。芝山巖も決して安全な場所ではなく、叛乱勢力による暴動が頻発すると、周辺の住民たちは繰り返し避難を勧めました。しかし彼らは避難せず、死を覚悟した上で教育者として説得にあたることを選び、1896年1月1日、6名の教師と用務員1名が約100人のゲリラによって惨殺されたのです。危ないことが分かりながら決して逃げる事のなかった教師たちの責任感と勇気は、教育者としての模範と受け止められ、多くの人から敬(うやま)われました。戦前の日本人は勇気と責任感を持ち、「六氏先生」はその象徴的存在でありました。この「勇気と責任感」こそ、日本人が台湾で尊敬された最大の理由であると私は思っています。教育に命をかけた「六氏先生」の話は台湾ではよく知られ、慰霊碑には今も献花が絶えません。
彼らの台湾の教育にかける犠牲精神は「芝山巖精神」といわれて語り継がれ、殉職した6名の教師は「六氏先生」、そして芝山巖は台湾における教育の聖地とされています。
六氏先生の内の一人で山口県出身の「楫取(かとり)道明」は吉田松陰の甥に当たる人物で、楫取道明の母親である吉田松陰の妹が、来年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主役になっています。また、最年少で命を落とした「平井数馬」は、熊本県の済々黌(せいせいこう)出身で、語学の才能に優れ通訳官として赴任していました。熊本市内にある平井数馬の墓には李登輝元総統も墓参りに訪れています。
~結論~
台湾の近代化に全力を尽くし、台湾のインフラ整備のために犠牲になった日本の方々が台湾に遺した功績を、台湾の人々は忘れていません。その恩恵に心から感謝をし「滴水之恩、湧泉以報」(たとえ一滴の水でも受けた恩義は湧き出る泉として恩返しをする)という気持ちを持ち続けています。2011年3月11日に発生した東日本大震災に対する台湾からの200億円を超える巨額の義援金は、その99%が民間から自発的に差し上げられたものでした。その背景には、先に述べた「滴水之恩、湧泉以報」の思いがあるとみられます。
今日、台湾は世界一の親日国家であるといわれていますが、その要因の一つとして、台湾のインフラ整備のために犠牲になった日本の方々の恩に報いたいという台湾の人々の思いがあげられるのではないでしょうか。

次回の卓話
6月20日 「クラブ管理運営委員長・広報委員長・会員増強委員長・新世代奉仕委員長・幹事退任挨拶」
6月27日 「奉仕プロジェクト委員長・会長・副会長・S.A.A.退任挨拶」
クラブ行事
6月20日(金)「祝賀懇親会」
18:30~ 料亭「新茶家」
6月23日(月)「次年度親睦活動委員会」
18:00~ 加茂川
6月27日(金)「米山委員会」
18:00~ 熊本駅前タワーマンション最上階
7月11日(金)「千葉康博幹事慰労会」
18:30~ 菊本
7月15日(火)「2014~2015年度職業奉仕委員会」
18:30~ 「すがを」
7月23日(水)「2014~2015会員増強・ロータリー情報・職業分類合同委員会」
18:30~ 田吾作
市域・地区行事
6月14日(土)「日田R.C.創立50周年記念式典」
記念式典 14:00~17:30
日田市民会館「パトリア日田」やまびこホール
祝賀会 18:30~20:30
三隈川遊船
6月15日(日)「日出R.C.創立30周年記念式典」
記念式典 13:30~16:20
祝賀会 16:30~18:30
別府湾ロイヤルホテル
7月13日(日)「熊本東R.C.創立50周年記念式典」
式典 16:00~18:00
祝宴 18:00~19:30
熊本ホテルキャッスル
2F「キャッスルホール」
熊本火の国ローターアクトクラブ
地区行事
6月28日(土)17:30~、29日(日)~16:00
「第29回地区ローターアクト研修会」
亀の井ホテル別府
鎮西高校インターアクトクラブ
地区行事
7月26日(土)~27日(日)
「国際ロータリー第2720地区第30回(2014~2015年度)インターアクト年次大会」
宇佐市安心院文化会館
《今週の会報担当 渡邊 義朗会員》
井上 勝己会長
司会進行 千葉 康博幹事
歌 唱 君が代、星かげさやかに
髙森 郁子ソングリーダー
来訪者紹介
来賓・卓話者 台北駐福岡経済文化事處
處長(総領事) 戎 義俊氏
渉外課長(副領事)李 蕙 珊氏
熊本火の国R.A.C. 齊藤 友樹会員、春澤 清乃会員
米 山 奨 学 生 葉 (ようりょう)さん
留 学 生 早稲田大学 林 紀 全さん
熊本大学 梁 敏 珣さん
熊本大学 許 意 喬さん
会長の時間 井上 勝己会長
皆様 こんにちは。
今日は大勢のご来訪者を迎えております。私も今日の日をとても、とても楽しみにしておりました。皆さん方とゆっくりこの一時間を過ごしたいと思っております。
それでは、ご来訪者のご紹介をさせていただくわけですが、その前に、一点だけ、本日の例会の主眼を、少しだけお話をさせてください。
本日の例会は、国際奉仕委員会の日ということで企画をさせていただいております。まずもって、このことを皆様方にお伝えいたします。
それでは、ご来訪者のご紹介を致します。
本日の卓話者でございます、台北駐福岡經濟文化事處の総領事・戎義俊(えびすよしとし)様でございます。
このたびは大変ご多用の中を、熊本クラブの卓話を、快くお引き受けを頂きまして、誠にありがとうございます。
当クラブを代表致しまして、心からの感謝を申し上げます。
本日のお話し、大変楽しみにしております。日頃の思いを、どうぞ、熊本クラブの若い方々に、特に今日は、ローターアクトの若い方々にご来訪いただいております。どうぞしっかりとそのお心を、お伝えいただければ、とても有り難く存じます。
よろしくお願い致します。
また、戎総領事は福岡城西ロータリークラブの名誉会員でもございます。当クラブでは県外からご来訪いただいたロータリアンの皆様に対しては、記念品として熊本の伝統工芸品の一つであります「出世コマ」を贈呈する慣例となっています。熊本クラブへのご来訪の記念として、お受け取りいただければと存じます。後ほどお渡しさせていただきます。
続きまして、本日、遠いところを 戎様にご同行をいただいております、
同 渉外課長 李蕙珊塔様でございます。
また、台湾からの留学生で、台湾在日福岡留学生会2014年度会長をなさっており、 現在、早稲田大学大学院に在学の 林紀全さん、でございます。今日は戎総領事と一緒に、福岡から公用車で来ていただいております。ありがとうございます。
次に、熊本大学に、ご在学の 梁敏珣さん
同じく熊本大学に、ご在学の 許意喬さん
でございます。先日4月に開催されました「日台の交流の夕べ」でご一緒させていただいております。今日は、本当にありがとうございます。ゆっくりしていってください。
後ほど留学生を代表して、早稲田大学に在学 林紀全さん、には一言ご挨拶をお願いしたいと思います。
続いて、熊本県 環境生活部 県民生活局 くらしの安全推進課 青少年班 参事 田上清之様でございます。
田上様はグローバルジュニアドリーム事業の担当をされておられ、本年8月に小中高生25名を同行し、台湾に行かれる予定になっています。今日は是非、戎総領事のお話をききたいということで、ご来訪いただいております。
後ほど、グローバルジュニアドリーム事業のご紹介を含めてご挨拶をお願いしたいと思います。
続きまして、米山奨学生 葉(よう りょう)さん でございます。先週に引き続き、ご来訪をいただき、誠にありがとうございます。
最後になりましたが、熊本火の国ローターアクトクラブから2名の方にお出で頂いております。ご紹介します。斎藤友樹様、でございます。春澤清乃様、です。
お二人をはじめ熊本火の国ローターアクトクラブの皆様には、当クラブのことでいつも大変お世話になっています。ありがとうございます。
皆様方のご来訪を心から歓迎申し上げます。
皆様、どうぞ、ごゆっくりとお過ごしいただければと存じます。
本日のご来訪者は以上でございます。
会長の時間でございますが、冒頭に申しあげました通り、本日の例会は、国際奉仕の日ということで、本日の会長挨拶は、ご来訪者のご紹介に代えさせて頂き、国際奉仕委員会の副島委員長に、この後をバトンタッチしたいと思います。
ありがとうございました。
認証品贈呈 井上 勝己会長
国際ロータリーより新会員を推薦により與縄義昭会員へ認証品と贈呈

米山奨学金支給(6月分) 井上 勝己会長
米山奨学生挨拶 葉 さん
新入会員紹介
(推薦者 小堀 富夫会員)

氏 名 原田 耕一
生 年 昭和41年
勤務先 三井住友信託銀行㈱
役職名 熊本支店兼熊本中央支店支店長
趣 味 旅行、ゴルフ
入会2ヶ月以内会員紹介 千葉 康博幹事
岡 成也(熊本YMCA)
■出席委員会
出席報告
■委員会報告
雑誌委員会 丸山 明委員
ロータリーの友 6月号紹介
■トピックス
「国際奉仕委員会の日」
副島 隆国際奉仕委員長
今日は国際奉仕委員会の日ということで、ご挨拶をいたします。
現在、熊本県は、皆様ご存知の通り、いろいろな分野での台湾と熊本との交流を積極的に進めておられます。
特に教育の分野で言えば、熊本ロータリークラブそして熊本南ロータリークラブ、肥後大津ロータリークラブも同行し協力をさせていただきました、3年前の大津高校の台湾修学旅行をきっかけとして、本年は県内高校で、修学旅行先を台湾にしようという大きな流れが出て来ています。
大津高校は3年連続で台湾を修学旅行先として、素晴らしい教育成果を上げておられます。生徒たちも大きな夢と希望を持って帰ってきているようでございます。昨年の同校の修学旅行には、今日取材に来ていただいていますTKUの報道部の方々も同行取材をなさっていらっしゃいます。
当クラブでは3年前の門垣年度に新世代奉仕委員会が、「日台の高校生間の交流・学校間の交流について何かできるもの・あるいは具体的なお手伝いがあれば、これを検討すること」を事業目的に掲げ、当時の大津高校校長白濱先生に卓話者としてご来訪いただき、「物見遊山ではない、真の国際交流に繋げる修学旅行先は台湾が最適である」旨のお話をしていただきました。当クラブの皆様からも高い評価をいただき、具体的な協力・応援の一環として、この時の新世代奉仕委員会の委員長であった井上会長が、先ほどの3ロータリークラブの方々と共に、大津高校の修学旅行に同行されました。
本日はこのような経緯の中、3年度に亘る継続事業の一つとして、国際奉仕のための例会日とさせていただきました。官民が一体となって、将来を担う若い世代の人たちに、様々なことを伝えていこうとする事業に、少しでもお役に立てるならば、これこそロータリーの趣旨・精神にかなうものと言えると思います。本日は、そのような視点で、関係者の皆様のお話を、どうぞ、ごゆっくりお聞きいただければと思います。
最後になりますが、今までのお話の中でもお分かりかと存じますが、本日は、TKUそして、先週卓話をいただきました産経新聞社の方にも取材に来ていただいています。県の事業と台湾の戎総領事をはじめ台湾の官の立場にいらっしゃる方々との連携の様子、その連携の中に熊本ロータリークラブが協力していく姿を、少しでも報道という形で多くの方々に知っていただくことは、本当にありがたいことだと思います。
どうか最後までご清聴のほどよろしくお願い致します。
台湾からの留学生代表挨拶 林 紀 全さん

「グローバルジュニアドリーム事業について」
熊本県くらしの安全推進課青少年班 原田 清之氏

■スマイルボックス
中川 成洋副委員長
井上 勝己、千葉 康博、中島 敬高各会員 本日は、台北駐福岡経済文化弁事所より戎 義俊様ご一行に、卓話のためにご来訪いただいております。感謝のスマイルとともに、お話を楽しみにしております。また、留学生の皆様や熊本火の国R.A.クラブの皆様もようこそおいでくださいました。ゆっくりと楽しまれて下さい。
小野 友道会員 本日、アーンズクラブの皆様が熊本保健科学大学を職場訪問して下さいました。光栄です!!
上田 祐規会員 ①ロータリーから妻の誕生日に可憐なお花を戴き有難うございました。今年、傘寿を迎えた妻のプレゼントはロータリーのお花で代理としました。元気で年をとっていることに感謝しています。②九電の渡邊支店長さんの御栄転をお喜び申し上げます。少し淋しいですが、これからの御活躍をお祈り申し上げます。
小堀 富夫会員 原田耕一さんの入会を歓迎スマイルをいたします。原田さんはロータリーははじめてだそうなので、よろしくお願いをいたします。
目黒 純一会員 ①原田耕一さん、入会おめでとうございます。ゆっくりとしたロータリーライフをお楽しみ下さい。②本日13日(金)と20日(金)の2回欠席します。今日(13日)は韓国・テジョン市のテジョン大学で落成式典に出席してます。20日(金)は、服部胃腸科で定期検診を受けます。4日間入院です。
前原 健男会員 原田さんの入会を心より歓迎いたします。ロータリーライフを楽しみながら熊本のよい所存分にご堪能下さいませ。
原田 耕一会員 本日より、歴史と伝統ある「熊本ロータリークラブ」に入会させていただくことになりました、三井住友信託銀行の原田耕一と申します。初めてのロータリークラブへの入会となります。一生懸命に活動して参りたいと思いますので、皆様にはご指導の程よろしくお願い致します。
中川 成洋会員 本日、弊社の転勤発表がありました。私は引き続き熊本でお世話になります。引き続き熊本で働けること、転勤していく仲間への感謝の気持ちを込めてスマイル致します。
渡邊 義朗会員 九州電力の渡邊です。私、このたびの異動で福岡に転勤となりました。熊本ロータリー在籍は、2年間と短い期間でしたが、皆さまとお知り合いになれて本当に楽しく、充実した熊本生活を送ることができました。厚くお礼申し上げます。また、クラブ会報の委員の方々には、この1年間大変お世話になりました。お陰様で、つつがなく毎週週報の発行ができました。ご協力大変ありがとうございました。最後に、今後の熊本ロータリークラブのますますのご発展と皆様のご健勝を祈念し、心からの感謝の気持ちをこめてスマイルします。「大変ありがとうございました。」
■本日の卓話
卓話者紹介 木下 修例会プログラム委員長
氏 名 戎義俊様
生 年 1953年
学 歴 1972年-1976年 台湾私立輔仁大学日本語科卒業
1983年-1985年 私立慶応義塾大学研究生修士課程1年在籍
2013年3月31日から 台北駐福岡経済文化辨事處處長〈総領事〉
「台湾の『日本精神』から見た日台関係」
台北駐福岡経済文化事處處長(総領事)
戎 義俊氏

台湾人の「日本精神」に関して
一、日本と台湾の結びつき
半世紀にわたった台湾の日本統治時代。「蓬莱(ほうらい)の島」、そして「美麗島(びれいとう)」と呼ばれた台湾で日本人と台湾人がともに過ごした日々の歴史遺産は今も人々に親しまれ、台湾に息づいています。
日本と台湾、その結び付きが大変強いことは言うまでもありません。日本から台湾へ向かう渡航者は年間140万人を超え、台湾から日本を訪れる渡航者は2013年度の実績で230万を数えます。台湾の人口が2,300万人余りである事を考えれば、その数の多さが分かるでしょう。往来の多さだけでなく、心と心の結び付きが強いともよく言われます。東日本大震災の時に巨額の義援金が台湾から送られたことや、インターネットを通じての被災地応援のメッセージなど、日台の結び付きは想像を超えるものがあると言っていいと思います。
二、「日本精神」は台湾では固有名詞として定着している
最近、台湾で『KANO』という映画が大ヒットしています。KANOこと嘉農は正式名称を嘉義農林学校といい、1931年、台湾代表として甲子園に初出場、準優勝を果たした野球部のことです。映画は史実を基につくられており、日本人、本島人(台湾人)、そして原住民からなるチームを一つにまとめ上げ、当初は弱小だったチームを生まれ変わらせた指導者・近藤兵太郎監督の立派な人物像が描かれています。近藤監督役を演じているのは、日本の俳優・永瀬正敏さんです。
『KANO』を通して、日本の教育は素晴らしかったという事が分かりました。「日本の植民地時代を美化しすぎている」という批判もありましたが、台湾が中国に呑み込まれようとしている現在、台湾人が顧みるべきは、この映画で描かれているような「日本精神」であります。この「日本精神」に触れる事を通して、台湾人は中華思想の呪","じゅ">縛","ばく">から改めて脱し、「公」と「私」を区別する武士道的な倫理に基づいた民主社会を確立しなければなりません。「台湾人も日本人もこの映画を見るべきだ」と思い、私からおすすめさせていただきます。
「日本精神」とは台湾人が好んで用いる言葉で「勇気」「誠実」「勤勉」「奉公」「自己犠牲」「責任感」「遵法」「清潔」といった精神をさす言葉です。日本統治時代に台湾人が学び、ある意味台湾で純粋培養された精神として、台湾人が自らの誇りとしたものであります。「日本精神」すなわち大和魂は「拚命(ビヤミア)」「全力を尽くして事に当たる」「命を懸けて行動する」ことの象徴です。「拚」は台湾語で「全力を尽くす」の意味で、「打拚」というと「倦(う)まずたゆまず頑張る」すなわち「勤勉」に通じる言葉であります。
日本の近代教育を受けた台湾人が戦後、目にしたものは中国文化ですが、この時、台湾人は「日本精神」の優位性を見出(みいだ)したのです。そして自ら選んで「大和魂」で精神武装し、内外の厳しい環境を生きようとしているのです。彼らの「大和魂」はひとつの生活の知恵であり、台湾人の魂として生き続ける新たな精神文化なのであります。教育によって台湾に浸透した「日本精神」があったからこそ、台湾は中国文化に呑み込まれず、戦後の近代社会を確立できたと考えられます。私の母は、昔の日本人の先生は、この日本精神で接してくれたと言いました。だから私たちも多少なりともその日本精神というものに染まっているのです。
三、「日本精神」を体現した人物
台湾の農業改革で大きな貢献をした水利技術者の八田与一のことを台湾で知らない人はいません。八田先生は干ばつが頻発していた台湾南部の嘉南平野を徹底的に調査し、灌漑設備が不足していることを指摘して、当時としては世界最大規模である「烏山頭ダム」の建設事業を指揮しました。その後、フィリピンでの灌漑調査のために乗った船が米潜水艦に撃沈されて八田先生は亡くなりましたが、遺骨は台湾に戻り、烏山頭ダムのほとりに眠っています。ダムのほとりの八田先生の銅像とお墓は今では国が整備した公園となって、国民から親しまれています。
日本は1895年4月に台湾総督府を開庁し、そのわずか3ヶ月後の7月に、「教育こそ最優先すべきである」として台北郊外の芝山巖というところに最初の国語学校(日本語学校)「芝山巖学堂」を開校しました。現在では芝山巖は台湾教育発祥の地とされ、「六氏先生」の慰霊碑が建立されています。「六氏先生」というのは、匪族に襲われて殺された6人の日本人教師のことです。危ないことが分かりながらも決して逃げる事のなかった教師たちの責任感と勇気は、教育者としての模範と受け止められ、多くの人から敬(うやま)われました。戦前の日本人は勇気と責任感を持ち、「六氏先生」はその象徴的存在でありました。この「勇気と責任感」こそ、日本人が台湾で尊敬された最大の理由であると私は思っています。「日本精神」というものを究極にするのならば「勇気と責任感」に集約されるのではないかと常々思うのです。教育に命をかけた「六氏先生」の話は台湾ではよく知られ、慰霊碑には今も献花が絶えません。
「八田与一先生」「六氏先生」、他にも台湾のために自らを犠牲にした方々が大勢おられます。彼らに共通するのは「日本精神」を体現した人物であるということです。
これから、日本にも台湾にも、この「日本精神」が脈々と継承され、そしてお互いにますます輝いてもらいたいと祈願します。
四、昔の日本人は素晴らしかった
(一)研究熱心
日本人がすごいところは、何かを研究する時にとことんやることです。何かを真似する時には、日本人はそれを自分のものにして、更に改良を加えてまた別のものを作ってしまいます。しかし、台湾人は見た目だけしか真似できません。外観だけ真似をして、あとは出来るだけ手抜きをするのです。日本人は違います。これはいいと思ったら、グループで一生懸命研究して、その原理を求めて、自分でまたそれに基づいて研究を進めて、更に別のものを作るのです。そこのところが私は立派だと思います。
それから、日本人はお金と時間をかけてでも新しいものにチャレンジします。そして、もう一つ私が立派だと思うことは、日本人はチャレンジしたものを公にして皆で研究します。昔の日本人は、緊急時には皆で力を合わせて、一つのものを四つに分けて、みんなで頂いたものです。自分だけがいっぱい得られればよい、自分だけが大きくなりたい、餓死したくない、という人は少なかったのです。台湾人も苦労してでも、一口のものを半口に減らしてでも人にあげます。
(二)けじめを重んじる
それから、日本人は「けじめ」を重んじます。「はい」といった事は最後まで全うします。日本人は、必ず約束を守ります。そういうふうに私たちは日本人を見てきたのです。
(三)素朴な宗教心がある
昔の日本人が素晴らしかったのは、前の代の教え方が良かったからではないかと思います。つまり、当時の日本人にも更に昔の日本人にも、いわゆる儒教の精神が生きていました。特定の宗教というより、生かされていることをお天道(てんとう)様に感謝し、お天道様に恥じないように生きようという素朴な宗教心があったからこそ、昔の日本人は素晴らしかったのだと思います。
五、今日における日本の若者の問題点
(一)今の日本の問題点は、平和すぎて将来に対する夢がないことなど色々ありますが、一番の問題点は、日本人には、生かされていることに感謝するという素朴な宗教心がないことではないでしょうか。だから自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのかが分からないのではないでしょうか。
(二)今の日本の青年は裕福すぎて考えが甘くなっているのではないかと思います。今の日本の若者は感謝を知りません。喜びを知りません。今、自分がこんなに幸せな国家に住んでいるのにそれを当たり前と思ってしまい、幸せを幸せと思えないのです。正にこれこそが不幸なことではないでしょうか。単一国家でやってきた日本人に生まれたことを、日本の方々は心から感謝しなければならないと思います。この世界には、国を二つにされた経験を持つ国家というものがほとんどですけれど、日本だけが二つにされていないのです。戦国時代といった内乱はありましたが、外国から二つにされた経験はないのです。例えば、中国は八つに分かれていました。ドイツは東西、朝鮮は南北、ベトナムも南北です。私たち台湾人にいたっては、一時国籍のない人間という立場に立たされていたのです。ですから、皆さんは日本人であることに感謝し日本という国を大切にして欲しいと心から願います。
六、台湾と日本、二つとも立派になってほしい
いつも日本の地図を見ていてつくづく思うことがあります。自然の神様は国の形でその国の生き方を教えているのではないかと。ある時にふと地図を逆","さか">さにして見ると、日本が龍に見える、そして台湾はまるで龍を踊らせている火の玉のようだと思いました。この時、この日本という龍について行けば東洋は立派になるんだなと思いました。台湾と日本は同じ火山脈(かざんみゃく)でつながれていて、切っても切れない強い強いつながりがあるのです。
日本がしっかりしなければ、東洋には平和は来ないと私はずっと信じています。日本の経済がよくならないと、世界の少なくともこの東洋の経済は良くなりません。日本という国が強く立派になったら、台湾も立派になります。日本の経済が立ったら台湾の経済も良くなります。そして台湾が良くなったら日本も更に伸びます。
日本と台湾、二つとも立派になって欲しい―これが私の心からの願いです。日本の皆さんが本当に自信を取り戻して、日本のために努力をして欲しいと思います。もちろん台湾も努力を続け、お天道様から見られても恥ずかしくないように立派な国を作っていきたいと思っています。日本と台湾、これからもお互いに切磋琢磨してまいりましょう。
台湾の近代化のインフラ整備のため
犠牲になった日本人たち
~前書き~
今から100年少し前、日本統治時代と呼ばれる1895年からの50年間、かなりの日本人がフォルモサ・麗しき島と呼ばれていた台湾に渡りました。
1898年、第4代総督児玉源太郎の民政長官として赴任した後藤新平が台湾で行った近代化政策は、「生物学の原則に従う」ものでした。元来医者であった後藤は、新領土の社会を一つの生命体として捉え、生き生きとした生命力を引き出す進め方を選択しました。台湾の社会風俗などの調査を行い、その結果をもとに政策を立案していきました。
その具体策として後藤は、台湾の人々の暮らしを豊かにする産業を興すと同時に、港湾、鉄道、道路、上下水道など基本的なインフラの整備に総力を結集しました。そのために内地から各分野で最も優れた人材が呼ばれました。
(「台湾の礎を築いた日本人たち・緒方英樹 著」より抜粋)
これから申し上げる6名の日本人は、自らの命を台湾のインフラ整備のために捧げ、犠牲となられた方々です。ここで簡略に6人の物語を紹介します。
まず始めに「八田与一」技師です。1886年に石川県金沢市で生まれた土木技術者で、1910年、24歳で台湾に渡りました。34歳から10年の歳月をかけて台湾南部の烏山頭に当時東洋一といわれた烏山頭ダムを作り、15万ヘクタールの嘉南平原に灌漑用の水路を張りめぐらせ、不毛の地と呼ばれていた平原を台湾最大の穀倉地帯にかえました。その灌漑用水路の長さは16,000㎞(地球半周分の長さ)に及び、日常的な生活用水にも困り苦しんでいた60万人を超える農民の生活を助けました。ダム完成の一年後には、作業着姿の八田与一の銅像が人々によってダムを見下ろす丘の上に設置され、その功績と精神は後世に伝えられています。
八田は、その後も台湾各地で産業開発に参画していましたが、1942年、南方開発派遣要員として船でフィリピンに向かう途中、アメリカ海軍潜水艦に撃沈され56歳で亡くなり、遺骨は台湾に戻りました。その3年後、終戦をむかえた年の1945年9月1日、32年間八田と暮らした烏山頭で妻の外代喜(とよき)夫人は夫の後を追うように烏山頭ダムの放水口に身を投げました。享年45歳でした。八田の銅像の後方には夫妻の墓碑が建てられ、ダム湖のほとりで烏山頭ダムを見守っています。八田の命日の毎年5月8日には地元の人によって慰霊祭が催され、近年建設された八田記念公園には、外代喜(とよき)夫人の銅像も設置されました。その除幕式には八田技師の長男の嫁にあたる女性が一族を代表して出席されるなど、交流は脈々と受け継がれています。
2人目に「末永仁(すえながめぐむ)」技師です。1886年に福岡県の旧筑紫郡で生まれました。1910年、23歳で台湾に渡り、台中の試験農場で「台湾蓬莱米」の開発改良に心血を注ぎ、自己を顧みず台湾のために尽くされました。1937年からはボルネオ島のサラワク王国に招かれ稲作指導を行っていましたが、指導に邁進するあまり滞在中に結核を患い、1939年台湾に戻りました。その後、台湾での作業中に実験田","でん">で倒れ療養を続けましたが、同じ年の1939年12月に53歳でこの世を去りました。
台湾の風土に適した台湾蓬莱米を開発し台湾の農業を大きく変えた末永技師は「台湾蓬莱米の母」といわれ、台中農事試験場内には、胸像が建てられています。また、出身地である福岡県の農業試験場農業資料館と、大分県の大分県立三重総合高等学校にも胸像が設置されています。
3人目は「飯田豊二」技師です。1873年に静岡県で生まれました。1911年38歳の時、台湾南部の高雄と屏東の境を流れる高屏渓にかける下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋を設計し架設工事に携わりました。工事中に何度も見舞われた豪雨や増水の対処や、寝食を忘れるほど仕事に没頭し続けた結果、下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋の完成を目前に過労による病(マラリア)に倒れてしまい1913年の6月に、鉄橋の完成を見ることなく40歳で亡くなりました。彼の功績を讃えて建てられた飯田技師の記念碑は、今でも下淡水渓(かたんすいけい)鉄橋を見守り続けています。
4人目は「進藤熊之助」技師です。1874年に茨城県で生まれました。1899年、25歳で台湾に渡り、大変困難を極めた阿里山森林鉄道の測量と建設に携わり情熱を傾けました。その優秀な仕事ぶりが認められ、阿里山作業所の技手(ぎて)から技師に昇格するも、1914年2月に、鉄道修復工事中に材木運搬車が脱線して重傷を負ってしまい、数日後に息を引き取りました。40歳でした。彼は、優れた技術を持つだけでなく誠実で勤勉な技術者であり、私利私情を捨てた働きは多くの人の心を打ち、その功績を讃えるために350人の有志によって寄付金が集められ、嘉義公園内に記念碑が建てられました。
5人目は、「松木幹一郎(まつきかんいちろう)」です。1872年、愛媛県で生まれました。後藤新平の信頼が篤く、1929年57歳で台湾電力の社長に就任し、中断していた日月潭の水力発電事業を再開させ、精力的に水力発電工事に携わりました。自ら歩き回って実地調査を行い、ついに1934年、当時アジア最大の発電量となる水力発電所を完成させました。日月潭第一発電所と第二発電所の完成のため尽力し、1939年、67歳の時に、脳溢血で急逝しました。過労といわれています。一年後の1940年には、その功績を讃えて日月潭に銅像が建てられました(戦時の金属供出により銅像は失われ、現在の胸像は新しいもの)。
後に日月潭第一発電所は大観水力発電所と改名され、その発電量は現在でも台湾の水力発電全体の半分以上を占め、この発電所がなければ今の台湾はないと語り継がれており、「台湾電力の父」といわれています。
6人目は「明石元二郎(あかしもとじろう)」です。1864年、福岡県で生まれました。1918年に第7代台湾総督となり、亡くなるまでの1年4ヶ月の在任中に台湾電力株式会社を設立し、水力発電所の計画を立案、調査に着手しました。また、日本人と台湾人の共学制を採用するなどの教育改革や南北縦貫道路や鉄道の充実など後の台湾の発展に欠かせない大きな業績を残しました。しかし1919年7月、公務で日本に渡る洋上で病に倒れ、郷里の福岡で55歳で亡くなりました。明石の遺骸は「もし自分の身に万一のことがあったら、必ず台湾に葬るように」との遺言通り、福岡から台湾にわざわざ移され、現在も台湾に眠っています。
明石が短期間の在任中に着手した日月潭水力発電事業は、第一次世界大戦による経済不況や関東大震災による影響で10年間中断されていましたが、先に述べました松木幹一郎によって再興され16年がかりで達成され、台湾の工業化を促しました。日月潭水力発電は、1898年から1906年までの8年8ヶ月間、民政長官として台湾の土台を築いてきた後藤新平が描く台湾インフラ整備のクライマックスともいえる大事業でありました。
これまで台湾の近代化のインフラ整備のため自己を顧みず犠牲になった6名の日本の方々の物語について紹介しましたが、備考としてインフラ整備のためでなく台湾の教育のために犠牲になった6名の教師を紹介します。「六氏先生」というのは、日本統治が始まってすぐの1895年7月、「教育こそ最優先すべき」と台湾に設立された小学校「芝山巖学堂(しざんがんがくどう)」で、抗日事件により殺害された6人の日本人教師、楫取(かとり)道明(山口県出身38歳)・関口長太郎(愛知県出身37歳)・中島長吉(群馬県出身25歳)・桂金太郎(東京都出身27歳)・井原順之助(山口県出身23歳)・平井数馬(熊本県出身17歳)のことです。
当時の台湾では日本統治に反対する勢力が激しい抵抗を続けていました。芝山巖も決して安全な場所ではなく、叛乱勢力による暴動が頻発すると、周辺の住民たちは繰り返し避難を勧めました。しかし彼らは避難せず、死を覚悟した上で教育者として説得にあたることを選び、1896年1月1日、6名の教師と用務員1名が約100人のゲリラによって惨殺されたのです。危ないことが分かりながら決して逃げる事のなかった教師たちの責任感と勇気は、教育者としての模範と受け止められ、多くの人から敬(うやま)われました。戦前の日本人は勇気と責任感を持ち、「六氏先生」はその象徴的存在でありました。この「勇気と責任感」こそ、日本人が台湾で尊敬された最大の理由であると私は思っています。教育に命をかけた「六氏先生」の話は台湾ではよく知られ、慰霊碑には今も献花が絶えません。
彼らの台湾の教育にかける犠牲精神は「芝山巖精神」といわれて語り継がれ、殉職した6名の教師は「六氏先生」、そして芝山巖は台湾における教育の聖地とされています。
六氏先生の内の一人で山口県出身の「楫取(かとり)道明」は吉田松陰の甥に当たる人物で、楫取道明の母親である吉田松陰の妹が、来年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主役になっています。また、最年少で命を落とした「平井数馬」は、熊本県の済々黌(せいせいこう)出身で、語学の才能に優れ通訳官として赴任していました。熊本市内にある平井数馬の墓には李登輝元総統も墓参りに訪れています。
~結論~
台湾の近代化に全力を尽くし、台湾のインフラ整備のために犠牲になった日本の方々が台湾に遺した功績を、台湾の人々は忘れていません。その恩恵に心から感謝をし「滴水之恩、湧泉以報」(たとえ一滴の水でも受けた恩義は湧き出る泉として恩返しをする)という気持ちを持ち続けています。2011年3月11日に発生した東日本大震災に対する台湾からの200億円を超える巨額の義援金は、その99%が民間から自発的に差し上げられたものでした。その背景には、先に述べた「滴水之恩、湧泉以報」の思いがあるとみられます。
今日、台湾は世界一の親日国家であるといわれていますが、その要因の一つとして、台湾のインフラ整備のために犠牲になった日本の方々の恩に報いたいという台湾の人々の思いがあげられるのではないでしょうか。

次回の卓話
6月20日 「クラブ管理運営委員長・広報委員長・会員増強委員長・新世代奉仕委員長・幹事退任挨拶」
6月27日 「奉仕プロジェクト委員長・会長・副会長・S.A.A.退任挨拶」
クラブ行事
6月20日(金)「祝賀懇親会」
18:30~ 料亭「新茶家」
6月23日(月)「次年度親睦活動委員会」
18:00~ 加茂川
6月27日(金)「米山委員会」
18:00~ 熊本駅前タワーマンション最上階
7月11日(金)「千葉康博幹事慰労会」
18:30~ 菊本
7月15日(火)「2014~2015年度職業奉仕委員会」
18:30~ 「すがを」
7月23日(水)「2014~2015会員増強・ロータリー情報・職業分類合同委員会」
18:30~ 田吾作
市域・地区行事
6月14日(土)「日田R.C.創立50周年記念式典」
記念式典 14:00~17:30
日田市民会館「パトリア日田」やまびこホール
祝賀会 18:30~20:30
三隈川遊船
6月15日(日)「日出R.C.創立30周年記念式典」
記念式典 13:30~16:20
祝賀会 16:30~18:30
別府湾ロイヤルホテル
7月13日(日)「熊本東R.C.創立50周年記念式典」
式典 16:00~18:00
祝宴 18:00~19:30
熊本ホテルキャッスル
2F「キャッスルホール」
熊本火の国ローターアクトクラブ
地区行事
6月28日(土)17:30~、29日(日)~16:00
「第29回地区ローターアクト研修会」
亀の井ホテル別府
鎮西高校インターアクトクラブ
地区行事
7月26日(土)~27日(日)
「国際ロータリー第2720地区第30回(2014~2015年度)インターアクト年次大会」
宇佐市安心院文化会館
《今週の会報担当 渡邊 義朗会員》
Posted by 熊本ロータリークラブ事務局 at 15:39│Comments(0)
│週報